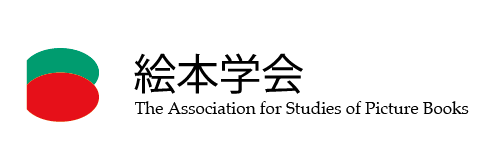[第20回]絵本学会大会・報告
[第1日目]5月3日(水)
15:45~16:15 研究発表Ⅰ-C 7号館7206教室
座長:甲斐聖子・松本育子
旭山動物園の飼育係であったあべ弘士は、動物園を退職後、野生動物が生息する地をめぐり、そこに生きる野生動物たちを独自の視点で絵本の世界に表現した。その第1作目がサバンナを舞台にした『ライオンのよいいちにち』(佼成出版社 2004)である。この絵本は、あべの25年にわたる飼育係としての経験とアフリカ体験が融合された作品であり、それまでの「動物園ガイド」を中心とした絵本から物語絵本という新境地を開き、動物絵本作家としての位置が固められた時期の作品と考えられる。
「動物園で動物たちと日本語で対話してきた」と述べるほど動物たちと深く関わってきたあべが、アフリカの大自然とともに生きる野生動物から受けた感動を、物語としてどのようにつくったかについて、「大自然の描き方」、「主人公のライオン像」、「擬人化表現」の3つの視点から考察することで、あべの独自性にアプローチした。
16:15~16:45 研究発表Ⅰ-C 7号館7206教室
ブルーノ・ムナーリ(Bruno Munari 1907-1998)はアーティスト、デザイナーであり、美術教育の分野でも様々な功績を残した。造本や構成に工夫を凝らした、子どものための本も複数出版している。
ムナーリは当初、未来派の作家として活動していた。同時にデザイナーとして仕事をする中で、子どもの本の制作にも関わるようになる。ムナーリの初期の児童を対象にした本である『ムナーリの機械』(河出書房新社,2009年,原書1942年)を取り上げ、絵本を本格的に作り始める以前のムナーリの活動を振り返る。また、その後に出版されたしかけ絵本「ムナーリの1945シリーズ」(全9巻,フレーベル館,2011-2012年,原書1945年)は、ムナーリが絵本の世界へ足を踏み入れるきっかけとなった。この絵本の特徴と共に、ムナーリの子どもに対する考えやムナーリにとって絵本がどのようなものであったかを考察した。
16:45~17:15 研究発表Ⅰ-C 7号館7206教室
近年、科学の分野でも数多くの絵本が出版されており、その隆盛の一因には写真家の活躍がある。今発表では埴沙萠(1931-2016)の絵本作品『きのこ ふわり胞子の舞』(ポプラ社、2011)を取り上げた。埴の写真はキノコの本体「子実体」よりも「胞子」に着目している点が特徴的である。胞子の写真はまず『植物記』(福音館書店、1993)に収録され、CD-ROM付き図鑑『植物のくらし』(偕成社、 2010)には絵本作品とほぼ同じ写真や動画が見られる。また、絵本作品の構成にはキノコの生態入門としてのストーリーがあり、そこには編集者の方針が大きく関わっている。生命の営みの一瞬を、美しくドラマチックに表現することにこだわった写真家の個性が、絵本の形態と出会い、互いに相乗効果を生んだ例として発表した。テーマの面白さが評価され、対象とする科学絵本の定義や、より深い考察が今後の課題として指摘された。
第1日目C室では3つの発表がありました。発表はどれもPPTを上手く活用し、分かりやすさという面で優れた配慮がされていました。はじめは、北海道えほん研究会による継続的な研究の発表で、アフリカ滞在を経て生まれたライオン三部作を、あべ弘士の動物絵本作家としての位置を獲得する重要な作品と捉え、うち一作について3つの観点から作品分析をした結果報告でした。つぎの養田もえさんの発表は、ムナーリの絵本作家としての仕事について、20代での未来派芸術家として培った思想や、子どもへのまなざしを著書や発言を手掛かりに考察を行ったものでした。フロアからも有益な情報を得るなど今後の研究に期待が持たれる展開となりました。最後の大橋慈さんの発表は、埴の絵本研究を核に考察を行い、科学絵本の物語性や芸術性について問う内容でした。絵本制作過程における編集者の役割に注目するなど多面的に科学絵本を捉える試みがなされていました。各発表後には、活発な質疑応答もされました。一例として大橋さんの発表の際にフロアから、図鑑や知識の絵本と科学絵本の違いについての質問がされ、発表者だけでなくフロア共通の課題として考える機会となりました。