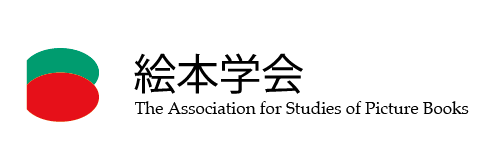子どもたちは絵本の世界に全身で飛び込む
正置友子
過去数回のリレーエッセーは、News 44 号で書かれた澤田精一氏の「振り返ってみると」からリレーが繋がっているようです。そのエッセイのなかで、澤田氏は、「絵本の世界で評論家と呼ばれる人は過去にもいなかったし、今もいないのではないか、1 冊の絵本をめぐってのクリティシズムにはなかなかお目にかからない」、と書かれています。澤田氏が提起されている問いは、「絵本の世界では、ちゃんとした評論家は過去にも現在にもいないのではないか」というものでした。編集者の澤田氏にしてみれば、自分が精根込めて世に送り出している作品を、まともに評価してほしい、1冊の絵本にきちんと向かい合って、評論を書いてほしい、という切々たる思いがあってのことと推察されます。
それを受けて、45 号の村中李衣氏は「絵本を語るそのなかに」というタイトルのもと、女子受刑者と絵本を読み合うという、目下関わっておられる経験を通して、絵本には、絵、ことば、画面構成のすべての要素の中から立ち上がってくる『声』がありこと、そして受刑者のひとりのAさんが、絵本を読み込んでいくうちに、絵本の奥にある「声」を聞き取り、Aさん自身が、その「声」は、自分の内側の「声」だと語っていることを書かれていました。村中氏からバトンを引き受けた46 号の灰島かり氏は「絵本の声を探して」と題して、絵本を肉声で読むときの「声」について書かれています。灰島氏は、児童養護施設を訪れ、小学校低学年の子どもたちと絵本を読む経験を通して、一人の少年との出会いについて触れています。小学校2 年生のR君が絵本と出会うには、誰かが絵本を「声」にして読むことのことがあったからではないかと、「声として絵本が存在すること」の意味を考えています。
村中氏や灰島氏が、絵本論と関わったところで、「声」ということばを取りだされていることに私は共感を覚えます。おふたりとも、「絵本」を一つの作品として取り出し、論ずることが可能だとわかりつつ、生身の人間の「声」を持ち出さずにはいられなかったところに、絵本への関わり方が出ているような気がします。一冊の「絵本」が「絵本」として存在しつつ、一方、他者の関わりが加わることで「絵本」の多様な面が見えてくるのではないか、ということではないでしょうか。絵本という表現形態が、多様な読者対象を可能にすることから、ある読者は、その絵本の中から自分に呼びかける特別な「声」を聴きとることができたり、ある読者は、絵本の中から独特の読みを発見することができたりします。ある絵本について、自分なりの読み込みをしていても、他の人たち(あかちゃんや、子どもたち、大学生や高齢者の方々)と読んだとき、思ってもみなかった感想、視点、出合い方を聞き、その絵本についての別からの見方、多層性、一層の深さを教えていただくことがよくあります。
私も長年、1 冊の絵本についてのちゃんとした作品論が書かれてこなかった、と思ってきました。そして、自分の勉強不足や、理論構築力の弱さは棚にあげて、作品論を書きたいと長年思ってきました。フロイトやメルロー=ポンティなどの心理学、哲学、思想理論などを使えば、理論的な作品論が書けるのではないか、とも思っていました。他の芸術分野(文学、美術、音楽、建築など)では、そういう理論からの作品論は成立しています。しかし、絵本となると、理論だけで作品を切っていくことができないのではないか、そうしたら、大事ななにかが零れ落ちてしまうのではないかという危惧を感じてしまうのです。全く感覚的な言い方ですが、絵本の本当においしい部分をこぼれさせないで、そして多面体としての絵本の質を傷つけないで、1 冊の絵本を「論」に組み込めるだろうかという怖さが残ります。
このように思うのは、私の場合、子どもたちとの40 年以上にわたる絵本読みの体験があるからです。子どもたちの「身体的な読み」の深さに幾度となく圧倒され続けてきました。大阪の北部に広がる千里ニュータウンの一隅で、1973 年以来、青山台文庫を主宰してきました。今年40 周年を迎えます。ここで、子どもたちと絵本(詩や物語も含め)を読んできました。紙幅の関係上、子どもたちとの絵本読みの例をひとつだけあげてみます。
マリー・ホール・エッツの『海のおばけオーリー』を読んだとき、私の前に坐っているのは、小学校低学年の子どもたち10 名ほどでした。ほとんどが男の子で、学業よりも活きの良さや面白い個性が目立つ子どもたちでした。『海のおばけオーリー』は、見開きにすると横44cm ×縦30cm の大型絵本であり、白黒、こまわりで描かれています。私はこの絵本が非常に好きでした。絵本のなかでは数少ない大冒険ものの絵本です。絵と言葉により、実におおらかにダイナミックに語られており、行きて帰りし物語としての枠組を持ち、安心して、絵本の世界に入り、冒険し、出てくることのできる絵本です。
あざらしの子のオーリーは、アメリカの東海岸の母親のもとからミシガン湖の南端の都市シカゴの水族館に売られます。初めは見物人を喜ばせていたのですが、やがて母親を思い出し、食べることもできなくなります。衰えていくオーリーの姿に水族館の館長はいたたまれなくなり、飼育係にオーリーを殺すように指示します。飼育係は、木槌を取り上げ、アザラシの子を一打ちしようとしますが、どうしてもできません。そのとき、オーリーが頭をあげます。湖の波の音を聞いたからです。察した飼育係は、自分の判断で、オーリーを湖に放します。その後に続く「湖におばけあらわる」騒ぎは、人間の誤解や噂が拡大していくおかしさと恐さを描いています。オーリーは、自分を探していた飼育係と湖で再会、彼の言葉「おかあさんのいる海へおかえり」を理解し、北の海に帰ることを決断します。ここまでが、27 ページにわたる138 のこま絵によって語られます。ページを開くと、見開き2 ページにわたる大きな絵(地図)が描かれています。ここまではこまわりで描かれてきた画面が、ここでぱっと一枚絵になるので、一層大きな広がりに見え、非常に効果的です。
この見開きで、オーリーの大冒険が一挙に語られます。五大湖の内の4 つの湖(ミシガン湖、ヒューロン湖、エリー湖、オンタリオ湖)を縦断して泳ぎ切り、オンタリオ湖から流れ出ている大河セント・ローレンス川を北へとくだり、北の海をぐるりとまわって(『赤毛のアン』の舞台であるプリンス・エドワード島の北側を泳いで)、ノバスコシア半島の東海岸に沿って南下し、ついにアメリカの東海岸に辿りつき、おかあさんと再会します。絵本の1 番の絵と143番の絵の間にはほんのちょっぴりの違いしかありませんが、この間には、オーリーの大冒険があります。
この作品の魅力のひとつは作品世界のスケールの大きさにあります。オーリーが泳ぎ切った距離、その距離がカバーしている面積の広がりを知っておいた方が、物語を深く理解することに繋がります。そこで、絵本を読み始める前に、世界地図を用意しました。日本と五大湖では、それぞれの形状は違うものの、小学生たちもおおよその広がりを頭に入れてくれたでしょう。
さて、上記した見開きシーンで、オーリーが延々と泳ぐ箇所を読み進んでいたときです。私は聞いてくれている子どもたちの側の空気が違ってきていることを感じました。異様ともいえる緊張感のようなものが、子どもたちから立ちのぼってくるのです。絵本から目をあげて、子どもたちを見ました。そこには、いつもは元気者の子どもたちが、緊張しきった顔でからだをこわばらせて坐っていました。顔面蒼白の男の子もいました。誰もひとことも発せず、空気を吸うのも忘れているような子どもたちの表情でした。子どもたちは全員、絵本の世界で必死で泳いでいたのです。子どもたちはだんだん、自分の力が尽きるのを感じていました。もう、あの湖の岸で横になろう。そうしたら死んでしまうかもしれない。もう二度とおかあさんにも、おとうさんにも会えないかもしれない。ぼく、もっとがんばりたいけど、・・・もうだめだ。もう、だめだ。あっと気がついたときには、私の目に、エリー湖やオンタリオ湖を一列になって泳いでいる子どもたちが浮かんできました。私は、目をまた絵本へと戻し、子どもたちの声にならない声を自分のからだへと飲み込み、子どもたちの蒼白な表情を自分のからだのなかへと受け取りながら、やっとの思いで、最後のページを読み終えました。
私にとって、この絵本は、冒険物語でした。楽しむことができる、素晴らしい「おはなし」の絵本でした。しかし、子どもたちにとっては、身を持って主人公になり、本当に冒険する絵本だったのです。このことは、子どもたちは、感覚や思考の一部だけで絵本や物語を楽しむのではなく、からだ全体で、絵本の世界に飛び込むことを物語っています。子どもたちの絵本の世界の堪能の仕方(怖いくらいのまるごとの飛び込み方)を見ていると、とてもじゃないけど、私の薄い作品論は書けないと思えてくるのです。大きな湖を泳いでくれたあの子たちは、今、30 代に入ったころです。風のたよりに「あの子がお父さんになったよ」と聞くと、私が選んだあかちゃん絵本3 冊を届けることにしています。