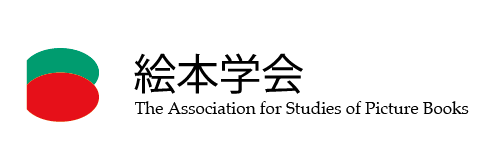夢三題
内田 麟太郎
前々から、イースト・プレスの筒井大介さんは変わった人だなァとは、思っていたけれども‥‥。
いきなり個展の葉書が同封されてきて、手紙には「この人の個展を見て、絵本テキストを書いてください」とあった。ほにゃららら。変わった人をいくらか尊敬したがるわたしは、東中野のポレポレ座へ中野真典展を観に行った。会場の隅にそれらしき三十代前半とおもえる男性が座っている。静かなたたずまい人だった。
(あの方が、そうであろう)
と思いつつも、わたしは挨拶はしなかった。だって、テキストが書けるものかどうか、自分でもワカッテオリマセン。
わたしは呆然として、その絵の前に立ち尽くした。
(こんな偶然があるのだろうか)
四十年近く、くりかえしくりかえし見ていた夢の場面がそこにあった。運命の出会いというものがあれば、これもそうだっただろう。それがどんな絵だったのかは語らない。少年の日の悲しみのままにと書けばいいのだろうか。いつもその夢から覚めると、
(なぜ、ぼくは、ここにいるの? なぜ、ぼくは、いつもここに来るの?)
という、とまどいと悲しみだけがしょんぼり残っていた。なんでやろ~、なんでやろ~。
しかし、その悲しい夢の謎も、つい二年ほど前の夢の中で答えが出た。そう、夢の中でデス。わたしは夢の中でつぶやいていた。
「わかった」
それから、同じ夢は二度と見ていない。不思議な体験だったけれども、それでもあくまでもワタグシゴトである。絵本にする気などさらさらなかったし、また、絵本にできるとも思えなかった。ただ、そんなことがワタシにはあったということだった。
その絵を買い求め、リビングに飾った。毎日、眺める。眺めて、つぶやく。
「こんな偶然があるのだろうか」
それから一月ほどして、
(書ける!)
という気持ちが、突然、ぐいと突き上げてきた。わたしは絵本テキスト『おもいで』を書いた。絵本の前半が墨一色というかなりきつい構成になっていた。
(大丈夫だろうか)
筒井さんはそのままで受け入れてくださった。編集者によっては、
「ここのところを、カラーにしてくれませんか」
と、求められてもおかしくはないところだろう。絵本はこれが初めてという中野真典さんは、みごとに描ききってくださった。それがどんな絵だったかはここでは語らない。ただ、あるところで、「編集者同士が会うと『おもいで』読んだ?」というのが合言葉のようになっていますよ」と、教えられたのはうれしいことだった。
長年解けなかった悲しい夢の謎が、夢の中で解けるという貴重な体験をした。しかも、そのことによって、悲しい夢からも解放されている。
二十代の終わりころ、ひたすらシュルレアリスムの本を読んでいた。いくらか取り憑かれたという感じである。例によってというのか、夢日記をつけ始めた。枕もとに大学ノートを置き、毎朝、目が覚めると記憶にある夢をノートにとる。そんな日をくり返していたら、前夜の夢の続きを見るようになった。連続劇です。これまた不思議な、いや、驚くべき体験だった。でも、わたしはこのノートを中断した。心身共にへとへとになり倒れそうになったからである。
(このままでは、危ない!)
夢については諸説あるようだが、この体験は、夢はでたらめがいいとわたしに囁いている。
よく女優の夢を見ていた。
竹下景子、沢口靖子、浅丘ルリ子、松坂慶子などなど。
そんな夢で目覚めると、その日はとても幸せだった。まさに薔薇色の人生デアル。その話を詩友三人の席(酒席です)で話したら、女性遍歴の豊富なYがこともなげにいった。
「そりゃあ、内田が気が小さいからだ。浮気したくても出来ない。女優の夢なら安全だからな」
なんたる、慧眼であろう。
わたしは深く頷くものがあった。いや、まことに思い当たることである。なるほど、隣の奥さんの夢を見ていたらかなり危ないものがある。
その夜から、わたしは女優の夢を見られなくなった。知の悲しみ、認識の悲しみといえよう。それが十年ほどぶりに薬師丸ひろ子の夢を見た。
「ひろ子さーん」
自分の寝言に、がばりと跳ね起きると‥‥。となりの布団で妻がうれしそうに笑っていた。妻の名前はひろこという。